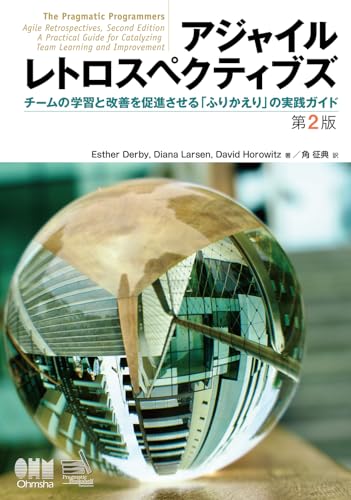『アジャイルレトロスペクティブズ』、以前から存在は知っていたし、人にも読め、と言っていたにもかかわらず、自分ではずっと読んでいなかったので、第2版の発行を記念して読んでみることにした。
特にアジャイルに限定する必要もなく、システム開発における作業の区切りのタイミングで実施する「ふりかえり」に関する構造や、ノウハウが詰まった1冊。
全体で約300ページの本だけど、まずは「ふりかえりの基本的な構造」を理解するためだけであれば「第1章 チームの検査と適応を支援する」と題された、最初の25ページを読めばざっと理解できる。
突き詰めていえば、後のページは「その構造をどうやってよりチームにとって適切に実行するか?」というノウハウ集と言ってもいいので、まずは最初の25ページを何度か読み込むことをお勧めする。
その時に「いま、自分たちはふりかえりができているか?」「必要な要素は揃っているか?」「上手くできているか?」という観点で何度か考えてみて、書き出しておくと良い...答え合わせは第2章以降にちゃんと用意されている。
で、その大事な第1章に何が書かれているか?というと、目次を抜粋すると以下のように書かれている。
ふりかえりの5つのフェーズ
フェーズ1:場を設定する
フェーズ2:データを収集する
フェーズ3:アイディアを出す
フェーズ4:何をすべきかを決定する
フェーズ5:ふりかえりを終了する
当たり前だけど、「何をすべきかを決定する」というのがポイントで、ふりかえっても何の行動にもつながらなければやる意味もないので、必ず何か変化点を設定する必要があるし、マネージャーはその変化に必要な環境(人・物・金)を提供する必要がある。
お気持ちだけではどうにもならないのです。
というわけで、良い本なのは間違いないので、読め、話せ、決めろ、行動しろ、という話でしかないのですが、自身を記憶を辿ってみると、キャリアの初期段階で、「ふりかえりのやり方」をちゃんと教えてもらった記憶が、無い。
おそらく経験や、他の人の真似をしながら少しずつ適切なやり方を学んでいったのだろうけど、「結局、投資の意思決定につながらない”ふりかえり”なんて意味なくない?」という当たり前の事実に到達するまで結構時間を使っていたような気もする。
しかし、おそらくそうではない”ふりかえり”はまだまだたくさん有るように思えるし、何を観点にふりかえっていいのか、なんでわざわざ時間を取って終わったことに対してあれこれ言うの?時間の無駄じゃない?という疑問を持っている人も多いと思う。
このあたりは完全に教育と成功体験の話になってくるので、単に「ふりかえりをしましょう」とだけ言ってもしょうがないので、この本のような「適切なやり方」を(実践できるかどうかは別として)、頭の中に入れておくのはいいかな、と思いました。
みんな、ふりかえりには一言有ると思うので、ぜひ読書会で、「あー」とか「うっ」とか過去をみんなでふりかえりながら読むといい1冊です。